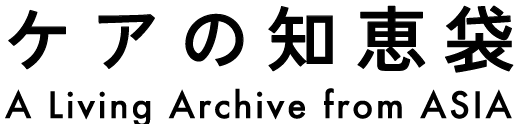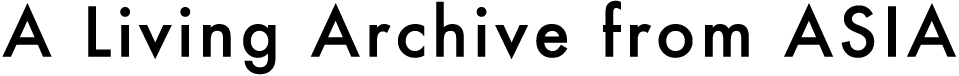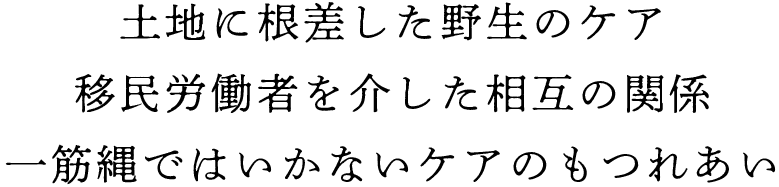対話のきっかけとしての「ケアの知恵袋」
国際交流基金は2023年から、美学者の伊藤亜紗・東京科学大学教授と「東南アジアの『ケア』プロジェクト」に取り組んできました。ウェブサイト「ケアの知恵袋」には、リサーチで訪れたインドネシアやフィリピン、ベトナム、そして台湾といったアジアの街角で見てきたローカルのケア実践を集め、文字通り「a living archive」として蓄積していきます。さらにケアについて考える対話のプラットフォームとして活用していく予定です。
リサーチに協力してくれたのは、研究者やアーティスト、プラクティショナー、行政やNGOの職員、アクティビスト、ケアワーカーやドメスティックワーカーとして働く移民労働者、障害者やインフォーマル居住区の住民など、実に多様です。彼ら彼女らがエッセイや論考、イラストやアニメーション、アートワーク、対談といったさまざまなフォーマットで、それぞれの地域のケア実践を共有してくれます。こうして共有されたケア実践に関するトークや座談会などのイベントも随時行なう予定で、その情報発信も本サイトで行っていきます。
具体的な知恵と実践としての「ケア」
私たちがこのプロジェクトで「ケア」と呼ぶものは、暮らしの中で日々直面するさまざまな困りごとに、どのように対応=ケアしていくのかという具体的な「知恵」と「実践」を指します。「ケア」と聞くと、多くのひとは看護や介護、福祉の文脈での実践を思い浮かべるかもしれません。他者への「思いやり」や「優しさ」といったイメージを持っているひともいると思います。他者を思いやり、助け合うことがケアであることももちろんあれば、場合によっては相手と積極的に交渉し、駆け引きしながら落としどころを探ることもあります。
社会の仕組みとして作り上げられた法や制度も、困りごとへの解決策を提示する点で一種のケアです。一方で私たちが路地で目撃してきたインフォーマルなケア、つまりある社会やコミュニティ、親族・家族といった限定的な集団の中で慣習的に行なわれている、仕組み化されていない実践もあります。法制度のように汎用性のあるフォーマルなケアは効率的な反面、想定されたバリエーションの埒外にある個別事情には対応しきれないといった課題があります。インフォーマルなケアは、実際に起きている現状にあわせて即興的に対応できる柔軟性がありますが、そのリソースが個人に依存しすぎるという問題点があります。社会が仕組み化されていないケアばかりで成り立っていたら、人々は疲弊してしまいます。
フォーマルとインフォーマルなケアを行き来し、ともに社会を考える
高度に法律や制度を整備し効率的な社会運営を目指してきた国々であっても、それだけでは複雑化する課題に対応できないという現実に直面しています。仕組み化されたケアやルールにどっぷりと浸かってきた人々にとっては、柔軟で創造力や機知に富むインフォーマルなケアには多くの気づきがあるでしょう。既存の制度やルールでは解決できなかった社会課題へのアプローチに、インフォーマルなケアの工夫や知恵を取り入れていこうとする試みもあります。
一方で近年特に著しい経済成長を見せる国々にとって、その姿は数年後の自国の社会を写した鏡かもしれません。ほかの国・地域のケア実践を知るだけでなく、彼らが日常的におこなっているケア実践が、日本のような国々の外部のまなざしによって、どのような意義を見いだされているのかを知ることで客観化や相対化が可能になります。フォーマルとインフォーマルなケアを行き来することで、日本とアジア、そして世界の人々とケアについて考え、社会の将来やあり方を議論するのがこの事業の狙いです。
この対話事業の目的はもう一つあります。それはケアを巡るグローバルな「もつれ」を描き出すことです。日本で私たちが頼る制度化されたフォーマルなケアは、海外から働きに来た人々が支えはじめています。台湾では移民労働者の存在はより顕著です。母国では父や母であった彼ら彼女らの不在によって、担い手がいなくなった家族のケアを親族間やコミュニティのインフォーマルなケアが埋め合わせている構図もあります。複雑に絡みあうケアの「もつれ」にも光を当てながら、ケアと社会について一緒に考えていきませんか。
プロジェクト・ディレクション
国際交流基金